行灯の組み立て方
標準的な大内行灯の組み立て方をご紹介いたします。
(写真クリックで拡大表示します。)
まず、部品は全部揃っていますか?(部品の各名称はこちら)
足が3本、取っ手が1つ電気ローソクと電球、柱2本、ろくろに三角と火袋です。
では、はじめましょう。

最初はろくろに脚を差し込みます。
ろくろは真ん中の穴のほかに穴が3つあいている方を上にして置きます。
畳の上でされるのであれば、間にタオルでも敷くと畳に傷がいかなくてすみます。
結構力をこめて差し込みますので、脚は差し込み近くをもちます。
2本差し込んだところで、三角を取り付け、残った脚をろくろに付けます。
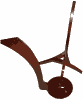
最後の足は少し差し込みにくいと思います。
どうしてもうまくはめれない場合は、足を3本とも差し込んで、三角を取りつけてください。
足を広げながらはめ込むとなんとかなるはずです。
堅くて足が最後まではまらないという場合は、何年か組み立てるうち木が緩んできますのでそのうちきっちりはまるようになります。
そこまで待てない方はやすりで削ってください。
無理やり入れようとするとろくろが割れてしまいますので、気をつけてください。

ろくろ、足3本、三角が組みあがったら、ひっくり返し脚が下、ろくろが上になるよう置きます。
ろくろに柱を差し込みます。
![]()
柱は、釘が撃ってある方が外側です。
これもぐりぐりしながら差し込みます。
この部分も最後まではまらなくても何年後かにはきちんとはまるようになります。(笑
ろくろの中央に穴が並んであいていると思います。
真ん中には小さな穴。
すぐ横に大きな穴。
これは電気ローソクを差し込むための穴です。
電気ローソクのネジをはずします。
![]()
ろくろの大きな穴に下のほうから差し込んで、いったん上に抜いたあとネジの部分を中央の穴へ差し込みます。
下からネジで締めて固定します。
![]()
で、電球をねじこみます。
火袋を取りつけましょう。
紐がついているほうが上です。
三本脚のうち、一本前に出るのが正面です。
絵の正面と合わせましょう。
柱を真ん中に通す感じでゆっくりとはめます。
ろくろにフックがついていますので、最後まではめたらそのフックを引っ掛けて固定しましょう。
火袋の紐を引っ張り上げ柱の釘に引っ掛けます。

釘の上に穴があいていますが、そこには取ってをねじ込んで取りつけます。

最後にろくろの下の電気ローソクのネジのフックに房を取り付ければ完成です。
